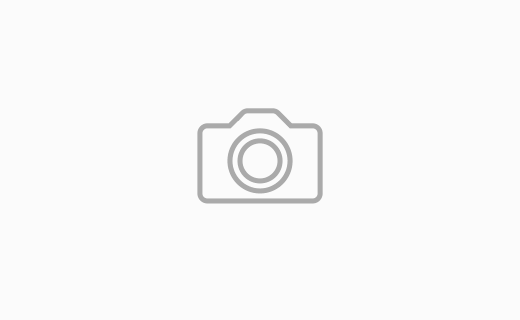- 作者: 鈴木清剛
- 出版社/メーカー: 小学館
- 発売日: 2009/01/08
- メディア: 文庫
- クリック: 4回
- この商品を含むブログ (10件) を見る
プログラマーとして働いている賢司は、
高収入、責任ある仕事も任され、彼女も居る。
端から見れば至極まっとうで順調な人生を送っていたが、
その実働く意味を見失っていた。
そんな折、
旧友の凌一が仲間2人と共にインディーズブランドを立ち上げる。
はじめは気分転換に彼らの作業場を訪れていたのだが、
3年半勤め上げた会社を辞めてからは、
次第に彼ら「あちら側の人間」に巻き込まれていく。
好きなモノを作って売る、というスタイルの彼らが
展示会に出展することを決めてから、不協和音が響きはじめ・・・
*****
1998年度三島由紀夫賞受賞、2002年に映画化された小説。
著者はコムデギャルソン勤務だったという経歴の持ち主だけに
洋服づくりに関する部分も詳細に描かれていて、
学生時代8年にわたって裁縫の授業を受けていた私には
非常に共感を持てる描写がたくさんありました。
ちなみに題名の「ロックンロールミシン」というのは、
もちろん「ロックミシン」のこと。
仕事が楽しいわけでも積極的にやりたいわけでもないが普通に仕事をする賢司と、
やりたいことをひたすら追い求める凌一。
2人が対称的に描かれています。
「オレ、この先もずっと、ファッションをやってるっていう予感だけはあるんだ。」
「・・・・・決心じゃなくて?」
「そう、予感だよ」
破天荒で計画性の無い凌一にため息をつきながらも、
好きなことをしている彼を羨ましくも思っている賢司。
しかし、それがビジネスである限り、
時には作りたくないものも作る必要があるわけです。
やりたいことだけをやることの難しさ。
「・・・自分で作ったものが好きって思ったり、かっこいいって思える気持ちが、何より大事なんじゃないの?」
「うん。オレもそう思う。作為的なのっていやだな。もともと、オレたち、つくりたいものをつくって売る、それだけの方向性だったじゃん」
売れなければ作れない、
しかし市場は時に自分たちの作りたいものではないものを求めることがある。
またあるいは、売れたら数を作らなくてはいけない。
ブランドなら、商品の「比率」のバランスも必要。
展示会に出展することでノルマが生まれ、そんな現実にぶち当たっていきます。
さらに、そこでわき上がってくるのがオリジナルとパクリの問題。
数を作らなくてはいけないけれど、創作というものはそう簡単ではないわけです。
「まずは自分の中に何かしら情報が入って、それが無意識のうちにアウトプットされるの。情報があってはじめて、人は表現できるようになるわけ。本当にオリジナルなものなんて、世の中にはないのかもしれない。あたしは日頃からそう思ってるけど」
「じゃあ、オレは、自分の中に溜まってる何かから引き出したい。はじめからパクるのなんてやだよ。でもってオレ的には、既存するものをまず否定することからはじめたい」
この問題は、多分もう人間がモノを作り始めたときから
延々と語られてきたことだと思いますが、ファッション界においても例外ではなく。
壁にぶち当たった時、彼らはどういう答えを導き出すのか?
それぞれの進む方向を示唆したところで、物語は終わります。
短編で、さらりと読めます。私は一時間くらいで読めました。
それでいて、上述したような問題を投げかけてくれる。
雰囲気としては青春群像劇とも言えるのでしょうが、爽快感はありません(笑。
読後になにか釈然としない思いが残る感じです。やりきれない、そういうもの?
映画はまだ観ていませんが、
ポップでシュールで、それでいてリアルでもあるあたり、
単館系の映画になる感じは分かります。映画も観てみたくなりました。