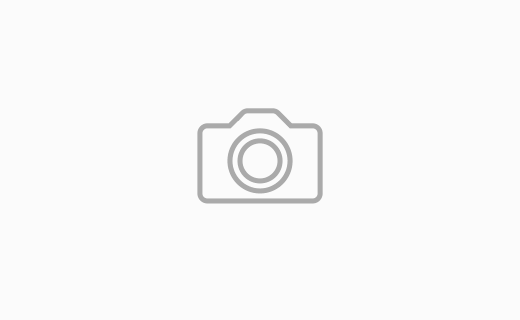- 作者: 川端康成
- 出版社/メーカー: 新潮社
- 発売日: 1989/11/17
- メディア: 文庫
- 購入: 1人 クリック: 37回
- この商品を含むブログ (39件) を見る
亡父の元愛人であるちか子に鎌倉円覚寺の茶会に招かれるまま、菊治は出かける。
令嬢をご紹介したいとのことだったのだがそこで父の愛人、太田夫人と顔を合わせてしまう。
亡き父の面影を残す菊治に父を重ね、無邪気に懐かしがる太田夫人。
母を苦しめる父の浮気相手として幼い頃あれだけ憎んだ女性にも関わらず
菊治は誘われるでもなく、あるいは抵抗するでもなく夜を共にしてしまう。
後日、太田夫人の面影を持つ娘、文子が許しを請いに菊治のもとを訪れる。
ちか子に紹介された美しい令嬢、ゆき子を気に入りつつも太田夫人のことが離れない。
「奥さん、奥さんには父と僕との区別がついているんですか。」
・・・菊治は夫人に言うよりも、むしろ自分の心の底の不安に向かって言ったのだった。
菊治は素直に別の世界へ誘い込まれた。別の世界としか思えなかった。
そこでは、父と菊治との区別などなさそうだった。
そのような不安が跡できざすほどであった。夫人は人間ではない女かと思えた。
人間以前の女、あるいは人間の最後の女とも思えた。
夫人は別の世界へはいってしまうと、
死んだ夫、菊治の父、菊治というような区別は感じないかと思われた。
菊治は罪の意識に苛まれながらもちか子が言うところの「魔性の女」、
太田夫人に次第に巻き込まれていくが、太田夫人は突然自らの命を絶つ。
図らずも太田夫人の死後、その存在は菊治の中で大きくなっていく。
そして次第に菊治は太田夫人を文子にだぶらせていき、体を重ねてしまう。
しかし文子は突然姿を消し、またもや菊治の前からいなくなってしまうのだった。
長い長い手紙を残して・・・。
昭和27年に「千羽鶴」が、29年に続編の「波千羽」が発表される。
なんともどろどろした陰気くさい話ですが(笑
川端康成の手にかかるとなんとも美しい情景になってしまうのです。
物語の鍵を握るのは、茶道具であり、名品の数々が登場人物と対比されて出てきます。
妖艶な光を放つ白い美しい志野を太田夫人にだぶらせ、
それを割ることで思いを断ち切ろうとする場面など、重要な要素になっています。
後半で菊治は当初の見合い相手、ゆき子と結婚するんですが、
その初めてのお茶会で使った亡父のゆかりの品、織部を売る下り。
あの茶碗にはあの茶碗の、立派な生命があるから、われわれを離れて生きてゆかせるんだ。
・・・あの茶碗自身は強い美しさで、不健康な妄執なんかまつわらせる姿じゃないんだが、
茶碗にともなうわれわれの記憶がいけなくて、茶碗をよこしまな目で見るというわけだ。
われわれと言ったって、せいぜい五六人に過ぎないよ。
昔から何百人の人が、あの茶碗を正しく大事にして来たかしれやしない。
あの茶碗が出てきてから四百年にもなるだろうから、
太田さんやおやじや栗本が持ったあいだは、茶碗の寿命から見て、ほんの短い間だ。
薄雲の通った影のようなものだ。健全な持ち主の手に渡ってゆけばいいんだ。
僕らが死んだ後でも、あの織部が誰かのところで美しいのは、いいと思うな。
持ち主が死に、茶道具は生き続けるという描写が他にもよく出てきます。
その名品たちの妖艶なまでの美しさと、一瞬にして割れてしまうはかなさを
人間の罪や欲、生や死になぞらえているんだと思います。
文学研究でもないのでただの私の感想ですが。
あと、ほんとに美しいと思ったのは、私たちが失ってしまった感覚が生き生きとしていること。
たとえば、初秋に蛍籠を置いていた菊治に対し、ちか子が
「そろそろ秋の虫籠の季節じゃございませんか・・・」
「・・・菊治さんがお茶をなさっていれば、こんなことはございませんよ。
日本の季節というものがあります。」
あとは、菊治がゆき子と思い出話をするときに
「ゆき子さんがあやめの帯をしめていたから、去年の五月ごろですね。」と言ってみたり。
なんか、こういう風情を持っていたんだよな昔は、と思うとちょっとうらやましいですね。
難しいことを考えないで、そういう視点で読むのも
古典(もう古典て言っていいのか?)の楽しみだと思います。